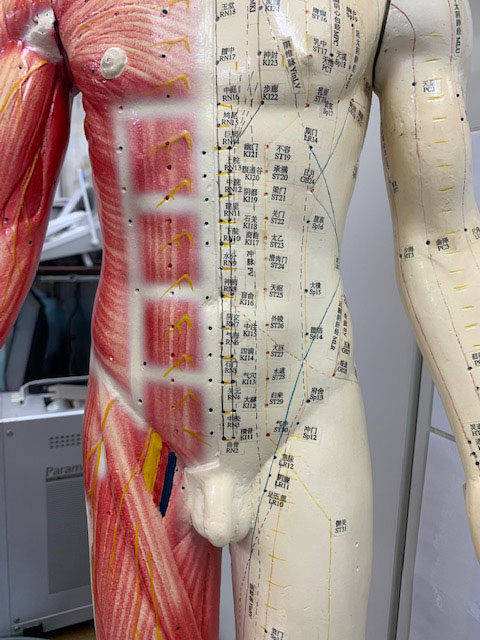2023年8月1日。写真は今年の博多山笠西流です。
陰陽と平
新古方薬嚢には
「薬、食には五味とは別に気キなる働きある物あり、この働きを大別して寒と熱となす。寒の微なるものを涼となし、熱の微なるものを温となす。
そのいずれにも偏せず特に気の働きを発せざるものを平となす。」と記述してあります。
東洋医学には陰と陽があります
陰から陽への変わり目を陰中の陽、陽から陰への変わり目を陽中の陰と考えています。
陰から陰中の陽へ、次は陽へ。
陽から陽中の陰へ、また陰へ戻ります。之を繰り返しています。
冬、陰から春、陰中の陽へ、次は夏、陽へ。
夏から秋、陽中の陰へ、また冬、陰へ戻ります。季節が繰り返すのと同じです。
人間の一生も、胎児は陰中の陽で、赤ちゃんは陽。
20代後半から陽中の陰、40代から陰になると考えています。
1日の推移も、夜中の3時頃より交感神経が高ぶり始め陰中の陽、日の出と共に陽。
午後を過ぎ太陽が傾き出すと陽中の陰、日の入りから陰に入ります。これを繰り返しています。
気温が一番高い14時頃は、陽中の陰で陰に入っていることが注目です。
気温が高いと言う結果や現症ではありません。
エネルギーの向き、太陽が昇って行っている陽、降りかけてくる陰。
スペクトルがどちらを向いているかで陰陽が決まる事が重要です。
陰陽と太極
病の進行状態を診る古方派の三陰三陽では
陽証では
表証である太陽病は、陰から陽への架け橋。太は架け橋の意味です。
陰中の陽と捉えます。陰と陽の架け橋のため、陽病ではありますが悪寒や寒気の表寒の陰証が残っています。
裏証である陽明病は、陽と考えます。悪寒や寒気はありません。身体の内も外も熱状態です。
脱水し血管内はドロドロで瘀血状態、腸にも熱証、子宮、卵巣も熱証、皮膚も熱証です。
その表証と裏証の中間、又は表証と裏証の両方を呈するのが少陽病と言います。
陰証では
太陰病は、陽から陰への架け橋です。陽中の陰と捉えます。
陰病なのに虚熱キョネツが残り、口唇の荒れ、手足の火照り、舌には湿った白苔などの陽証が残ります。
少陰病から本当の意味の陰病です。陰証になります。内臓機能の低下、心機能の低下、新陳代謝も衰え身体も冷えます。表裏共に寒になります。
生体と患部の陰陽
東洋医学の治療を行うに当たり、生体全体は陰証なのに患部は陽証と言うことが有ります。
例えば虚証の女性で子宮筋腫がある時などです。
虚証は陰証、子宮筋腫は瘀血で陽証です。
治療は瘀血処方を虚実を和らげたり、或いは1日の分量を減薬し対応します。
このように生体全体の証と病の証が異なる事があります。
生体全体の証と病の証が異なれば異なるほど治りやすい傾向にあります。
例えば皮膚病では
色白の桂枝加黄耆湯証の患者さんに脂漏性湿疹などの瀉心湯証である黄連、黄芩の組合せの柴胡清肝湯証などが出現した時などです。
生体全体の証と患部の証が異なるため治りやすい傾向にあります。
逆に生体全体の証と患部の証が近似なら治りにくく、治療にも時間が掛かる可能性が出てきます。
例えば温清飲証の患者さんに同じ解毒症体質の柴胡清肝湯証の脂漏性湿疹ができた時などです。
東洋医学での病と治療
病は、身体が陰か陽に傾くことにより生じると、東洋医学では考えています。
その陰陽を調和するのが東洋医学の治療です。
陰陽が調和されたバランスの良い状態が太極であり健康だと考えています。
太極を目指す
黄帝内経難経八十一難に
「実を更に実し、虚を更に虚せしめる事。不足を益々損じ、有余を更に益々増すような治法を行うなかれ」とあります。
神農本草経には
「寒を治すには熱薬を用い、熱を治すには寒薬を用いる」
虚実、寒熱など陰陽のバランスを整える治法をしなさいとの教えです。
太極とは陰も陽も何もない状態ではなく、陰と陽のバランスが良い状態です。
寒証には熱薬を、熱証には寒薬を。
湿証には燥薬を、燥証には潤薬を使います。
降の治療を例にすると
神経症や高血圧などの気の上衝に対して、何を用い気の上衝を下げるのか。
燥証では
燥証に気の上衝があれば、潤わし柔らかくし下げる五行の水、腎、鹹に配当される牡蠣や芒硝を用います。
湿証では
湿証に気の上衝があれば、乾燥し固めて下げる五行の火、心、心包、苦に配当される大黄や黄連を用います。
気の異常には気の上焦以外に気滞、気虚などがあります。
気の上焦は、他に発散剤を用い治す方法なども有ります。
バランスの取れた太極にすることが東洋医学の治療です。
食養生もまったく同じです。
誰にでも合うものなどありません。しいて誰にでも合うのは、民族が伝統的に守ってきた主食だけです。
平とは
では五気の寒、涼、平、温、熱の平とは何でしょう。
平とは太極で、寒と温が、虚と実など、陰と陽がバランスよく成っている状態だと考えられます。
漢方薬味では甘草が五気では平に成ります。処方では半夏厚朴湯などは五気ではなく虚実が平です。
糸練功や入江フィンガーテストが出来る先生は、半夏厚朴湯が実証にも虚証にも合う事に気付かれた先生もいらっしゃると思います。
半夏厚朴湯は、虚証には補剤として働き、実証には瀉剤として働いています。
生体が平の半夏厚朴湯を自分の身体に合わせ補瀉を使い分けています。不思議です。
漢方薬の植生
30年程前に、漢方生薬の培養をしている研究施設を訪れたことが有ります。
その研究所では当帰も川芎も同じ成分の培養液の中で育てていました。不思議でした。
当帰と川芎では成分組成が異なります。効能も川芎は上焦へ、当帰は下焦へ働きます。
しかし「植物は各々自分に必要な成分を根から吸収する」そうです。だから「異なった植物でも同じ培養液で育つ」とのことです。
その土地で、植物は自分に必要な成分をそれぞれが吸収しています。不思議です。
人間も同じなのかもしれません。